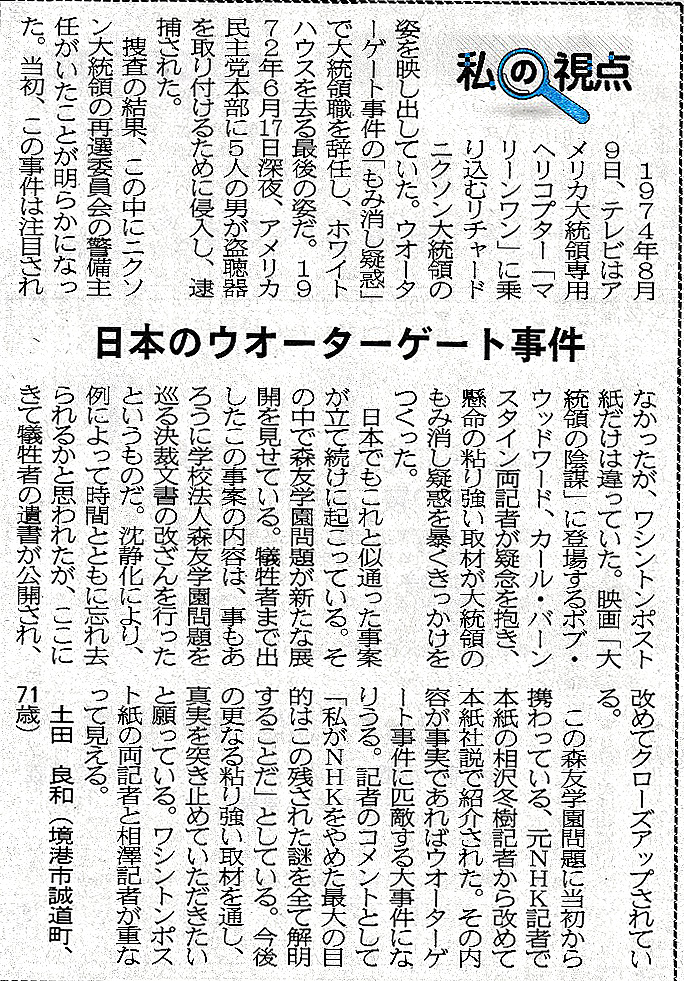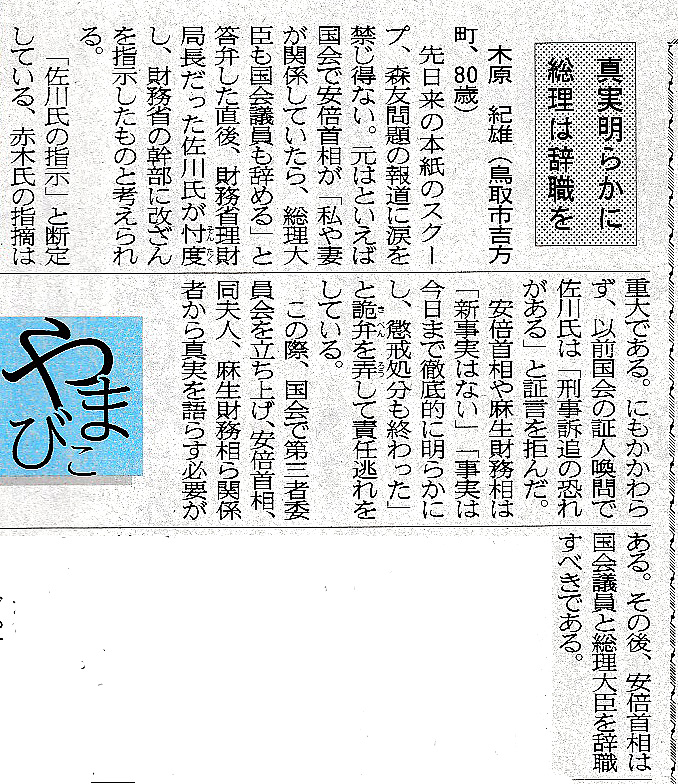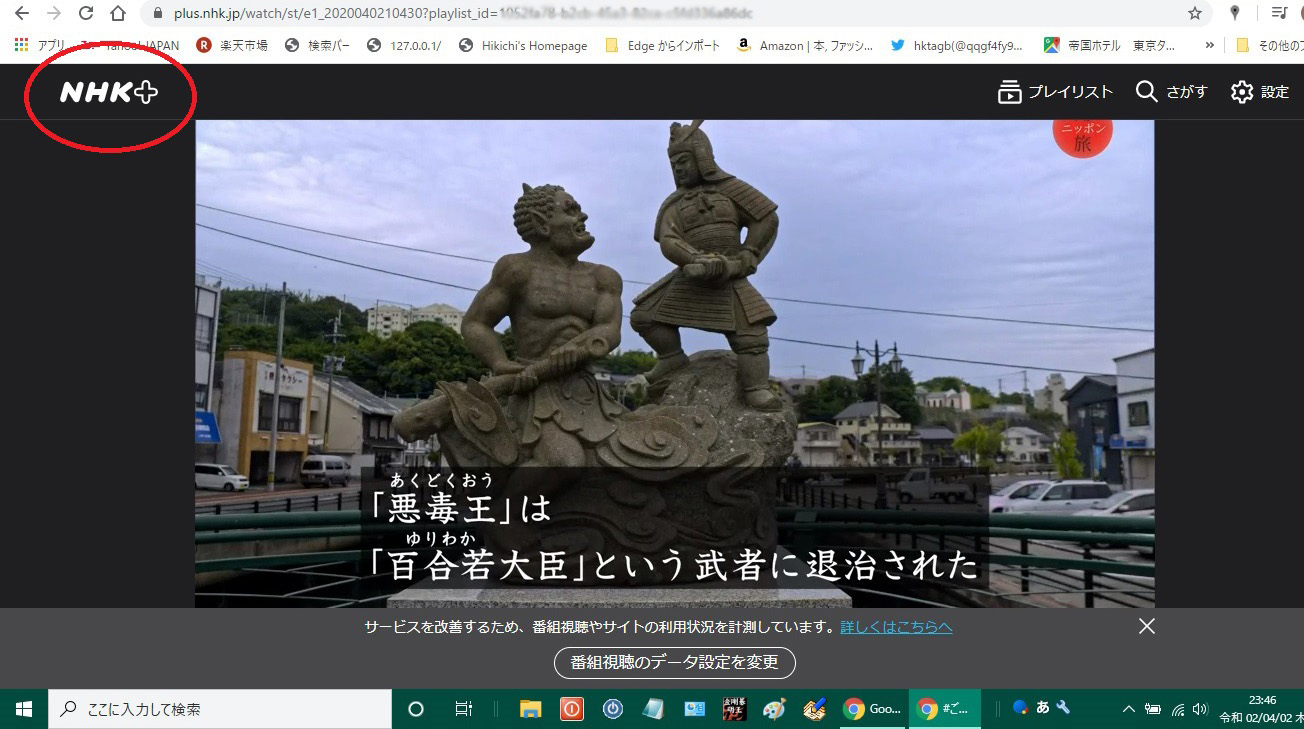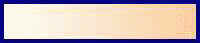愛犬に優しい人とその犬にめぐり逢いました。
この写真を撮影したのはかれこれ一ヶ月ほど前になります。
小さなゴムタイヤに水道の?エスロンパイプで組み上げた台車に
後ろ足が上手く動けなくなった犬を乗せて連れて歩いてしました。
この微笑ましい光景はブログに乗せるべきとパソコンを開きました。
最近は犬を連れて歩く人が多くなってきました、この少し前には
猫の首に首輪を付けい散歩している人を見かけました、世はまさに
ペットブームです。さて今は新型コロナウイルスの声を聞かない日がない毎日です、外出がしゅくせいされる中で私がほとんど毎日散歩している太閤ヶ平は普段は人通りが無いのですけど最近はたくさんの人と出会います。
犬も猫も人間も大変な時代になっていて早くコロナが終息(収束)することをを願う今日このごろです。
My Diary(by/JH4AGB)
日々の生活を気ままにつづった日記帳。
記事一覧
トップ
愛犬に優しい人とその犬にめぐり逢いました
鳥取県はついにコロナに汚染されました。
鳥取県はついにコロナに汚染されました。
4月8日までは日本で3県残っていましたが9日になってついにコロナが
鳥取県でも発症がわかり残念ですし、私は高齢なのでとても心配しています、でも私は尊厳死を認めてほしいと思っているのでコロナに掛かったら潔く心を静かに余命を過ごすでしょう。
ところで10日の日本海新聞に「日本のウォーター事件」とした投稿があり全く共感しました、令和2年度の予算委員会で、森友や桜問題を野党がひつように追求して無駄な国会を費やしていると散歩仲間が言っていますが、私はそうわ思いません、投稿者の意見に賛成です、今の安倍政権の忖度ぶりには呆れてしまいます、財務省の職員が自殺してもそのトップは栄転するは、裁判所の定年延長は勝手に解釈して自分の身の回りを固めてしまうのは腐れきったトップの末路だと思っています。我々はもうこれらを追求する能力も体力も有りませんのでタダ成り行きを見守るしかありません、でもこのコロナが安倍政権の味方をしているとは思いたくないし早く終息してほしいです。
追伸
14日に「真実明らかに総理は辞職を」が投稿されましたので追記しました。
NHKプラスが見えるようになりました
NHKプラスが見えるようになりました。
閲覧可能とはなったのですが閲覧したのは時間が遅かったのか
入り方が悪かったのかフイルターがかかっていました、昨日
ヤット閲覧可能となりました。写真は夜中に見た画面です。
あまり長時間の番組はリストに有りませんでした、今後充実
されるでしょう。
ヤット筆者のGoogleマップが表示出来るようになりました
ヤット筆者のGoogleマップが表示出来るようになりました。
バーチャル観光等に使用しているマップが灰色になって久しい(昨年末頃からか?)初めは単なるミスでいずれは正常に戻るとたかをくくっていましたが最近になり深刻化してきたので対応せざるを得なくなりました。
Googleマップは当初無料で使用出来ていたのですが2年ほど前からAPIコードを取得し課金(サービス有り)が必要となりました。通常筆者のようにマップを閲覧者が見るチャンスと時間が少ないうちは課金はサービスで処理され金は掛かりませんでした。
この度アレヤコレヤとチェックして何がなんだか分からぬ内にマップの灰色がなくなりました。ヤレヤレです。
4月に公開するバーチャルのGoogleマップをここに先駆けて公開します。
今年はどんな年になることやら先が思いやられます
今年はどんな年になることやら先が思いやられます。
大晦日に近くの火伏神社のしめ飾りを付けに行ったときに左の蝋燭立てを誤って壊してしまい、正月の2日に修理しました、蝋燭立てはとても古くて砂のような状態でセメントが付いてもすぐはがれそうでしたのでアルミの針金で縛りました。
そしてもう一つの修理は古くなった洗濯機、洗濯槽が傾いていました
機能的には異常が無くただ傾いているだけで、洗濯機の裏蓋を外すと洗濯槽を釣り上げている一本の支持が外れていました、外観上で分かる事なので支持棒を直しました、いつまで持つでしょうか素人の修理ではまた直ぐに壊れるでしょうが一時しのぎての正月でした。
突然の事だったので洗濯機の修理画像はありません、残念!!。
プロフィール
コンテンツ
リンク集
過去ログ
- 2026年02月 (1件)
- 2026年01月 (2件)
- 2025年11月 (2件)
- 2025年10月 (1件)
- 2025年08月 (1件)
- 2025年07月 (2件)
- 2025年06月 (1件)
- 2025年05月 (2件)
- 2025年04月 (1件)
- 2025年02月 (1件)
- 2025年01月 (1件)
- 2024年12月 (2件)
- 2024年11月 (2件)
- 2024年09月 (1件)
- 2024年07月 (1件)
- 2024年06月 (1件)
- 2024年05月 (2件)
- 2024年04月 (1件)
- 2024年03月 (3件)
- 2024年01月 (2件)
- 2023年12月 (2件)
- 2023年11月 (1件)
- 2023年10月 (1件)
- 2023年09月 (3件)
- 2023年08月 (1件)
- 2023年07月 (2件)
- 2023年06月 (4件)
- 2023年04月 (2件)
- 2023年03月 (1件)
- 2023年01月 (1件)
- 2022年12月 (1件)
- 2022年11月 (3件)
- 2022年08月 (1件)
- 2022年06月 (1件)
- 2022年05月 (1件)
- 2022年04月 (1件)
- 2022年03月 (3件)
- 2022年02月 (1件)
- 2022年01月 (1件)
- 2021年12月 (1件)
- 2021年10月 (4件)
- 2021年08月 (2件)
- 2021年07月 (1件)
- 2021年06月 (1件)
- 2021年05月 (1件)
- 2021年04月 (1件)
- 2021年03月 (4件)
- 2021年02月 (1件)
- 2021年01月 (1件)
- 2020年11月 (2件)
- 2020年09月 (1件)
- 2020年08月 (1件)
- 2020年07月 (2件)
- 2020年06月 (3件)
- 2020年05月 (4件)
- 2020年04月 (2件)
- 2020年03月 (1件)
- 2020年01月 (1件)
- 2019年11月 (2件)
- 2019年10月 (4件)
- 2019年08月 (1件)
- 2019年07月 (4件)
- 2019年06月 (3件)
- 2019年05月 (1件)
- 2019年04月 (5件)
- 2019年03月 (2件)
- 2019年02月 (4件)
- 2019年01月 (4件)
- 2018年12月 (2件)
- 2018年11月 (2件)
- 2018年10月 (3件)
- 2018年09月 (1件)
- 2018年08月 (4件)
- 2018年07月 (4件)
- 2018年06月 (5件)
- 2018年05月 (1件)
- 2018年04月 (5件)
- 2018年02月 (1件)
- 2018年01月 (1件)
- 2017年12月 (1件)
- 2017年11月 (4件)
- 2017年10月 (1件)
- 2017年08月 (2件)
- 2017年07月 (5件)
- 2015年07月 (2件)
- 2015年06月 (1件)
- 2015年04月 (3件)
- 2014年12月 (1件)
- 2014年10月 (3件)
- 2014年09月 (2件)
- 2014年08月 (2件)
- 2014年07月 (2件)
- 2014年06月 (1件)
- 2014年05月 (2件)
- 2014年04月 (3件)
- 2014年03月 (3件)
- 2014年02月 (1件)
- 2014年01月 (2件)
- 2013年12月 (1件)
- 2013年11月 (6件)
- 2013年10月 (3件)
- 2013年09月 (1件)
- 2013年08月 (3件)
- 2013年07月 (4件)
- 2013年06月 (3件)
- 2013年05月 (2件)
- 2013年04月 (4件)
- 2013年03月 (2件)
- 2013年02月 (2件)
- 2013年01月 (3件)
- 2012年12月 (2件)
- 2012年11月 (3件)
- 2012年10月 (5件)
- 2012年08月 (1件)
- 2012年07月 (5件)
- 2012年06月 (2件)
- 2012年05月 (1件)
- 2012年04月 (1件)
- 2012年03月 (3件)
- 2012年02月 (4件)
- 2012年01月 (2件)
- 2011年12月 (3件)
- 2011年11月 (4件)
- 2011年10月 (3件)
- 2011年08月 (4件)
- 2011年07月 (4件)
- 2011年06月 (3件)
- 2011年05月 (5件)
- 2011年04月 (3件)
- 2011年03月 (5件)
- 2011年02月 (7件)
- 2011年01月 (12件)
- 2010年12月 (10件)
- 2010年11月 (12件)