青谷の上寺地遺跡の紹介パート2
青谷の上寺地遺跡の紹介①は弥生時代後期の溝と木器溜まり。②は水田跡で紀元前300年代の炭化物があった。


③溝は建築材や舟を再利用していた。④田下駄や馬型木製品などの出土の様子。


⑤杭と板による構造物で水路の護岸と考えられています。⑥素掘りの溝で土器のかけらが見つかった。 ⑦弥生時代後期から古墳時代前期の溝と木器溜まり


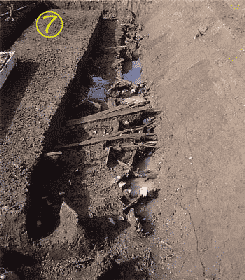
⑧木器溜まり、斧の柄や、農具などが見つかった。⑨奈良時代以降の溝や土抗が確認され祭祀具など出土
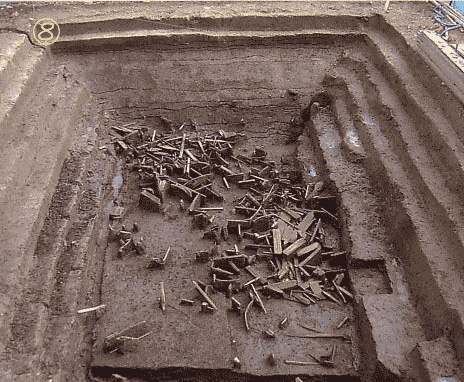

⑩弥生時代後期の土抗や、古墳時代後期の堀立柱建物跡。⑪炭化物の小豆(弥生時代の終わりごろ) 、⑫スタンプ文土器

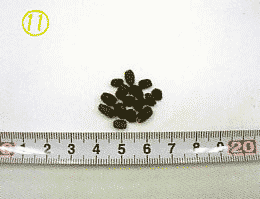

⑬琴板、⑭田下駄(年代測定結果西暦152年とでた)、⑮奈良時代に祭祀に用いられた馬形木製品。
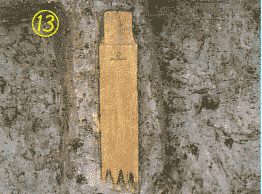

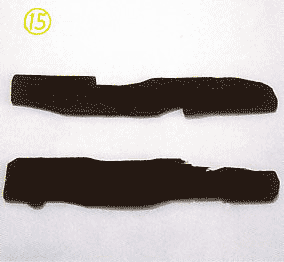
⑯舟を転用した水路の杭

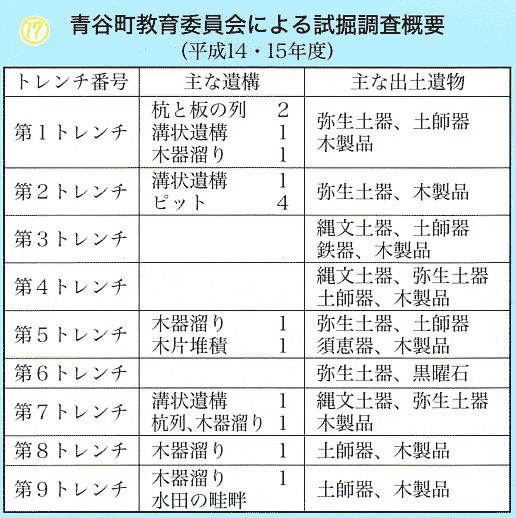

以上、青谷町教育委員会の資料より掲載しました。