私のオーディオ遍歴について
最初の写真は真空管式のアンプである。
B300と言って真空管でも最もシンプルな3極管の真空管でプッシュプル接続でパワーを稼いでいます。5極管と比べパワーは無いがシンプルさで本当に素直で爽やかな音がする。当時真空管からトランジスターへと移行するとき、トランジスターアンプはクリヤーだがとにかく音が硬いと言われていて長時間聴くと疲れたものでした。
真空管式のアンプやプリアンプ、FMチューナーなど色々作ったが、手元にあるのは唯一これだけである。
これはおおよそ10年前にキットで売り出していたものを作ったものです。やっぱり音は柔らかく、そして透明感がある。良き時代の昔がほのぼのと思い出される。今でも真空管式アンプにこだわる人はたくさんいる。
さて、本来のオーディオ遍歴だが、ここに改まって書くほどにのめり込んだ訳ではない。以前にも書いたが、常に金欠病に取り付かれていた関係で出来たことはタカがしれた事なので御恥ずかしい次第です。
機械いじりが好きだった事が良かったか悪かった、とにかく自分で作る事が面白く、何でもかんでも
一度分解しないと気が済まない性質で、当時の真空管式ラジオをばらしては組み立てたものだった
。
当時流行し出したステレオがどうしても欲しかったが、金欠病のため、安い5球スーパーラジオを2台並べて聴いていた、それも型違い、音響特性も位相もあったものではない。
位相を合わせようにも手の出しようがない。それでも一応ステレオということで御満悦だった。安いクリスタルプレーヤーをつないでいでのステレオだから、電気に感電する事しきり。当時のラジオはトランスレスだったから、2台のラジオを同時触ることは感電することにつながった。今は懐かしい。


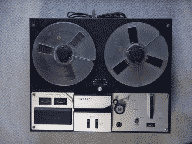
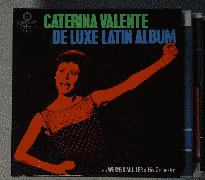

何とか金をためて6BQ5シングルだったように思うが、初めてのステレオアンプをようやく組み立てて聞いた、が、スピーカーは5球スーパーラジオの物で代用していたから、人様のステレオとは違い貧弱な音だった。時代はドンシャリの HiFi(高忠実度再生) 時代。パワーによる低音とシャリと響く高音への伸びが競われていた。ナショナルの20センチのスピーカーをようやく手に入れたが、箱は自作、このスピーカーは今も健在している。
P**** の 3 ウエイスピーカーボックスにはまっている。( P*** のウーハースピーカー腹の立つことに聞いているうちに変な音がし出して良く見るとコーンのエッジがウレタン製の為ボロボロとなりコーンが宙にういて鳴っていた。箱とMid とHiのスピーカーは健在。( 2番目の写真 ) 実に40年前の代物。スピーカーと箱とのマッチングがよくなかったのか、人様の16センチのスピーカーの方が良い音がした。


この16センチスピーカーは音のまとまりが良く捨てがたいものがあった。三菱のダイヤトーンは今でも記憶のなかにある。話は横道にそれたが、低音が貧弱でパワー不足は否めなく、6BQ5 PP アンプの製作意欲が沸いたが、アウトプットトランスが高くなかなか手が届かなかった。
ようやく手にして作り上げたアンプも、スピーカーと箱のマッチングが悪かったのか、こもったブーミーな低音だった。メーカー製のステレオが高度化していった時代で技術力と財力には勝てなかった。(サンスイ、パイオニャ、トリオ、三菱等家電メーカーが競ってステレオに力をいれた) 努力は空しく、自作の時代は過ぎ去った感があった。
オーディオ評論家はこのへんらから音響製品の組み合わせを云々しだした。アンプはどこ、スピーカーはどこ、プレーヤーとの相性はどこ、と盛んに評論した。
スピーカーは、全域にわたり平坦な特性を出すのが難しく、得意な分野で本領を発揮させようと音域を分担してのマルチスピーカー再生へと試みられた。当時は大きいのが流行で、部屋が狭いのに場所を取っていた。
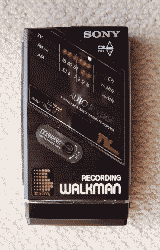
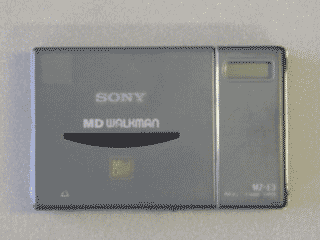
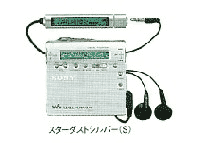


ステレオはトランジスターの時代となり、自作はなかなか難しくなっていったが、そのうちパワーアンプICなるものが世に出始め手軽にハイパワーアンプが作れるようななった。パワー部はブラックボックスでもその周辺のトーン回路、プリアンプ部、入力セレクターなど、プリント基板にフォトエッチングし、ステレオ雑誌のコピーが十分楽しめた。
10年前までそのアンプは使用していたのだが、
メーカー(SONY)製の魅力に負けたのと、トランジスターノイズが気になり、金も無いのに切り替えた。
この製品は4チャンネルで音楽ホールを再現できるものだったが、部屋との相性がよくなかったか、あんまりホールフェーズでは聞くことは無く普通のステレオで聞いていた。この少し前にCD が世に出始めていた。
それまではオープンテープデッキ(19cm/s)SONYのTC-350 にFMやレコードから録音したものを中心に聞いていた。
何しろ、レコードのような手間要らずと長時間再生が魅力なのと、けっこう良い音がして、人様のレコードを録音させてもらい、たくさんのテープライブラリー(4番目の写真)が出来た。
オーディオはまだ重厚なものの全盛時代で、今のようなコンパクトなコンポはまだ
世に出ていなかったが、カセットをレシーバーで聞くと言ったイメージの先駆けとなったのはSONYのウオークマンWM-F202でサルが聴いているCM で出世間を驚かせた。これがカセットレコーダーかと疑いたくなるような良い音に2度驚いた事であった。しかも単3電池1本で
の駆動でラジオ付であった。
その次はMD(MZ−E3/SONY)初代で、次の
MDは(MZ−R900/SONY)であるが、ポータブルの2代目で録音付きでLP対応で今も大活躍中である。今は再生専用の3代目も活躍中、初代はその当時としてはかなりコンパクトであったが重量があった、単3電池2本で駆動していたが録音は出来ないタイプだったので、すぐにMDデッキを買うこととなった。

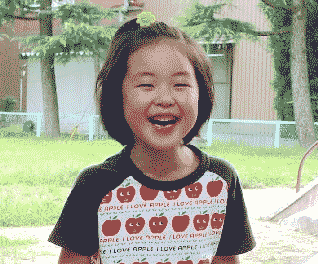



ウォークマンからMDがこの世に出るまで5年ぐらいかかったであろうか。MDの登場により、テープノイズとテープの巻きつきやヘッドクリーニングなどのわずらわしさから開放され、CDなみの音と長時間再生とランダム再生が可能となった。
考えが古いのか、昔の先輩諸氏のオーディオ装置に魅了されたのか、相変わらず、重厚長大な方向で、システムを少しずつ買い足していった。
買い足しに時間が掛かったため、システムが入り口から出口までそろった頃には、新シリーズが出たりで、むなしさが残った。
世間では、コンパクトなコンポが流行しだして、店先からも、大きいものは消えてしまっていた。
M D はまだLP 録音が出てなかったので、74分が最長だった。これを補完したり M Dへの編集に、DAT(デジタルオーディオテープ)が長時間の録音が出来て重宝した。テープも沢山出来たが、M D-LPの出現とともにあまり使わなくなった。
それにしても技術の進歩は目覚しいものがあり、MD-LPが発表されてそんなに時間がたっていなのに今度は45時間もの超長時間の録音再生が出現するとか、まさに驚きです。そして今やハードディスク内臓のiポッドなる物の出現で音楽業界は大きく変貌しようとしています。

